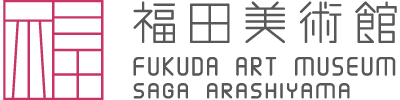栖鳳の時代 ~匂いまで描く
西の雄、京都画壇の竹内栖鳳
竹内栖鳳(1864-1942)は、伝統文化を千年以上に渡って育んできた街・京都に生まれた、近代を代表する日本画家です。 幕末に起きた戦火で京都の中心地が焼け野原と化し、荒廃していた頃に育った栖鳳は、まず江戸時代から続く日本画の技法の中でも、この地において主流であった「四条派」に習いました。その後円山派や狩野派、南画など他の伝統的な画風をも学び、さらにはターナーやコローなど当時の西洋画や写真の要素までも貪欲に取り入れます。栖鳳の「省筆」によって選び抜かれた線や画面に残された余白は、まるで栖鳳が生涯愛した俳句の世界の如く、人々の想像力に訴えかけます。
本展では、匂いや音・湿気までもが感じられると言われ、一世を風靡した栖鳳の動物画と風景画の大作をはじめ、師匠の幸野楳嶺(1844-1895)や四天王と称された同輩たち、個性豊かな教え子らの作品をご紹介します。かつて栖鳳のアトリエがあったここ嵐山で、彼らが生きた時代の息吹を感じて頂ければ幸いです。
作品リストはこちら(2021年2月19日更新)
第1章(1Fギャラリー)/京都画壇の革新

円山応挙を祖とする円山派と、その弟子・呉春に始まる四条派。その両方を受け継いだ画家である幸野楳嶺(1844-1895)は教育者としても名高く、多くの才能ある弟子たちを育てました。その中でも竹内栖鳳(1864-1942)、菊池芳文(1862-1918)、都路華香(1871-1931)、谷口香嶠(1864-1915)は四天王と呼ばれ、近代京都画壇の隆盛に貢献しました。栖鳳は楳嶺の下で円山・四条派の画技を修めた後、京都府画学校では狩野派や雪舟の筆法、南画までも模写して学び、それらを自在に組み合わせて新しい日本画を作り出そうとしました。その作風は様々な動物が混ざった妖怪に例えて「鵺(ぬえ)派」などと批判もされますが、彼は屈することなく探究を続け、渡欧して西洋絵画を目の当たりにし、その要素を取り入れます。帰国後発表した作品は「匂いまで描く」と称賛され、その地位を確立しました。第1章では、京都画壇を再興し新しい時代を築いた5人の巨匠の作品と、当時栖鳳に刺激を受けた京都市立美術工芸学校の画学生たちによる動物画なども、併せて展示いたします。
第2章(2Fギャラリー) /憧れの栖鳳先生

〜日本画は省筆を尚(とうと)ぶが、充分に写生をして置かずに描くと、どうしても筆数が多くなる。写生さえ充分にしてあれば、いるものといらぬものとの見分けがつくので、安心して不要な無駄を棄てることができる。〈『国画』2巻9号 昭和17年(1942) 〉
栖鳳は徹底した写生を行った上で厳選された線のみで描く「省筆」を用い、対象の本質に迫ろうとしました。また、絵の中の余白の取り方などの表現についても、たゆまず探究し続けました。
〜東洋流系の絵画は、画面に描かれた部分だけが全部とされないで、余白をも絵の一部と解釈されている。余白のあつかい方で、絵が活きもすれば死にもする。〈『国画』2巻9号 1942年〉
第2章では、栖鳳が極めた省筆と余白が印象的な作品を中心に展示します。また、栖鳳に学びつつ独自のスタイルを確立した、橋本関雪、徳岡神泉、村上華岳ら個性豊かな弟子の作品もご紹介いたします。
第3章(2Fパノラマギャラリー) /青の部屋

海や川、深い山々など、日本の自然を描くために青は欠かせない色です。古来日本では緑色も青と呼んでいました。第3章では栖鳳が群青で表現した穏やかな海の作品と共に、小野竹喬《黎明》や、池田遙邨《灯台道》など、栖鳳の弟子たちの中でも、青がとくに印象的な作品を特集します。また日本画の絵の具の中でも希少な群青・緑青の絵の具の実物を展示。栖鳳が活躍した当時の絵の具もご紹介いたします。
展覧会概要
主催福田美術館・京都新聞
| タイトル | 栖鳳の時代 ~匂いまで描く |
|---|---|
| 会期 | 2021年3月1日(月)~ 2021年4月11日(日) 前期:2021年3月1日(月)~ 3月22日(月) 後期:2021年3月24日(水)~4月11日(日) ※緊急事態宣言の解除時期によっては開始日が早まる可能性がございます。 |
| 開館時間 | 10:00〜17:00(最終入館 16:30) |
| 休館日 | 火曜(祝日の場合は翌平日) |
| 入館料 |
一般・大学生:1,300(1,200)円 ※( )内は20名以上の団体 料金 |